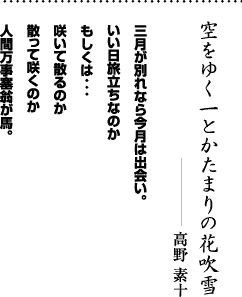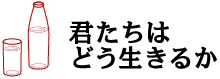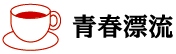|
|
||||
|

|
この本との出会いはラジオでした。毎晩、5分程度でしょうか、朗読は進んでいきます。聞くほどに引き込まれていきました。 「人間て、まあ、水の分子みたいなものだねえ」と主人公のコペル君は言います。そのあとに「人間分子の関係、編み目の法則」を発見し、次のような文章で、この物語を締めくくっています。 「僕は、すべての人がおたがいによい友だちであるような、そういう世の中が来なければいけないと思います。人類は今まで進歩して来たのですから、きっと今にそういう世の中に行きつくだろうと思います。そして僕は、それに役立つような人間になりたいと思います。」(本文298頁から) 65年以上も前に書かれた本ですが、内容は全く色あせていません。このようなものをプリンシプル(原理・原則)というのでしょう。 カルノが参禅するお寺の和尚さんが、「3歳の子供さんから、90歳のお年寄りまでわかる言葉で答えなさい」と、言われます。まさしくこの本は、小・中学生向きに書かれていながらも、大人にも十分読み応えのある本です。 カルノの座右の書です。ぜひ、ご一読を。 |
||||||
|
|||||||
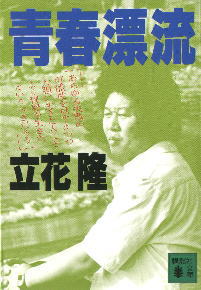
|
この本との出会いは、行きつけのバーのマスターからの紹介でした。 先日、新聞の「ひと」の欄の「動機が希薄でも、負けず嫌いだと頂点をきわめられるようだ」とのくだりに目が留まりました。この本に登場する11人の若者が、まさしくそのとおりです。 青春、朱夏、白秋、玄冬、著者は冒頭で、青春とは過ぎ去ってはじめて気がつくものである、と書いています。しかし、石原裕次郎は「生きてるかぎりは青春さ」とも唄っています。 「人生論は、もっぱら喫茶店やバーの椅子の上で語られると思っている人がいる。自分の人生とは無関係の論であると思っている人がいる。しかし、ほんとうの人生論は語るべき対象というよりは、実践すべき対象なのだ。」(プロローグ12頁から) 手前味噌で恐縮ですが、この11人の中に、拙連載で御登場いただいた、斉須政雄さんも出てこられます。どうぞおかわりで。 |
||||||
|
|||||||