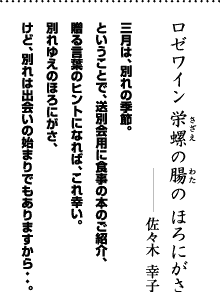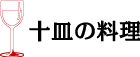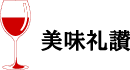|
|
||||
|
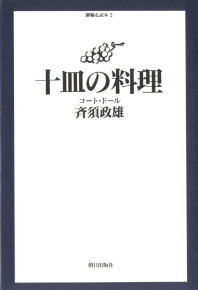
|
斉須政雄さんの名前をご記憶の『歯科技工』愛読者の方も多いかも。拙連載「ものづくり 名手名言」(2000年12月号)に、ご登場いただいたシェフです。 本の名を新聞広告に見つけ、すぐ取り寄せ、一気に最後まで読んでしまいました。読み終わっていても立ってもいられなくなり、この本を手に、東京・三田の「コートドール」を訪ねました。これほどまでに「食べてみたい」と思わせた本には、いまだかつて出会っていません。まさしく、その力はアペリティフ*!! 「最終的には皿にのっかってしまうと、同じ料理なら、誰が作ったものも同じように見えることがあります。三人の人間が同じものを作るときにどこがどう違うか。それは、段取りです。要所要所を押さえた段取り、操作が各人各様にあって、そこに個性が表われるのだと思います。じゃあ、操作における斉須の個性はなんなのだと問われたら、僕は、すべからく、最少限度で抑えることだと答えます。最少限度の時間と作業。なにごとも、必要以上にやることはないのです。ぎりぎりのタイミング、力の抜き具合。」(21頁から) 今回、読み直して、また食べに行きたくなりました。早く席について「いただきます」と言いたい! *アペリティフ:食前酒 |
||||||
|
|||||||
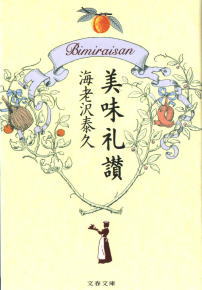
|
この書名を広告で見たときに、「オヤッ?」と思いました。『美味礼讃』といえば、かの有名なブリア・サヴァランの著した本です。「どんなものを食べているか言ってみたまえ。君がどんな人であるかを言いあててみせよう」と述べている、哲学の書ともいえる名著です。その書名を使うとは、恐れ多いなぁと思いつつ繙いたところ……、参りました。1993年3月2日に亡くなられた辻 静雄さんをモデルに話は展開していきます。そのたおやかなストーリーは、あたかも三ツ星レストランでフルコースを堪能しているかのような錯覚に陥らせてくれます。 「ブリア・サヴァランはこの本の中でこういっているの。『フランス人は、ほかの民族よりも、ただおなかがすいたから食べるという人間と、味をよく噛みしめて楽しんで食べるという人間を厳重に区別することに、非常な熱意を燃やしている民族である』。つまり、世の中には食べるということに関して二種類の人間がいて、フランス人はそのことに早くから気がついていたということなのよ。わたしの話が分る?」(158〜159頁から) 読み終わったときに、心から「ごちそうさまでした」と手を合わせました。 |
||||||
|
|||||||