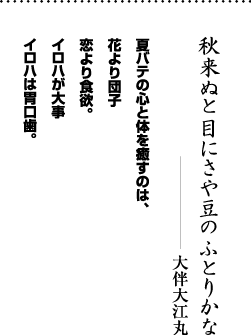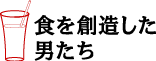|
|
||||
|
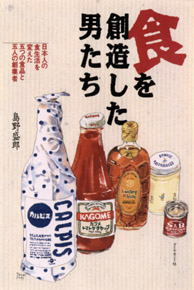
|
ケチャップ、カルピス、ウイスキー、マヨネーズ、カレー粉。今や、いずれの食品も、普段の食卓や冷蔵庫に見られるものばかりです。この本を読んで、初めて、これらすべての食品が輸入物ではなく、登場する五人の創業者によって創造されたものであることを知りました。 「マヨネーズに興味を持った董一郎は、その成分を調べてみると、卵と植物油と酢でつくられていることがわかった。さらにマヨネーズは、当時の日本人に欠けていた良質のタンパク質を含んだ栄養価の高い調味料であることを知った。こうして董一郎は、マヨネーズを商品化し、日本に普及させ、日本人の体格向上の一助にしたいと思うようになった。 これがキューピーマヨネーズ誕生の最初の動機である。」(137頁から) 『諸君はこのボーナスをどう使うか。どう使ってもかまわないが、私には二つのお願いがある。一つは一冊、本を買って読んで欲しいことである。いま一つは貯金などに回さないで欲しい。若いうちからコツコツ貯めようなんて了見では先が知れている。全部、使って人生体験をして欲しい』(83頁から) 本を読んだあとに、変わったことは、これら5つの食品の味です。歴史の味とでも言いましょうか。これら5つの食品に秘められた深い味が判るような気になりました。本を含めて、どうぞ御賞味あれ。 |
||||||
|
|||||||
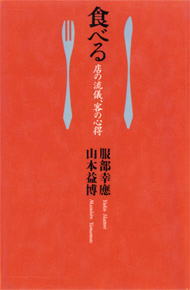
|
何を食べるかも重要ですが、どう食べるかもまた大切なことです。 「料理はその六割が技術です。これは受け継げます。錬磨していけば、ある程度は受け継げる。しかし『味』は違います。なぜか。それは人格が違うからです。」(服部幸應―28頁から) 「機械なら精度には限度があるけれど、人間のワザにはそれがないと思えてしまう。落語や他の芸人の世界にも共通するけれど、「一生が修業」のような、求めればもっと上へ上へと昇っていける。『食べる』も『作る』も、だからきりがないし、そういう世界じゃないかと。」(山本益博―112頁から) 前書きで、山本氏は「ものを“食う”のではなく、料理人のつくる料理を“食べる”というのはどういうことなのか?」と、まず問いかけています。食べることへの価値観や求めるものは、人それぞれでしょう。食べることに、より価値を求める人は、食べることを取り巻く環境、食材はもとより,調理法や器、雰囲気、そして口腔内環境にも、さらなる価値を求めるような気がします。口腔内環境に携わるものとして、食べるということをより真摯にとらえる必要があるように思えますが……。 |
||||||
|
|||||||