グラフィックデザイナーになろうと思ったきっかけは?
小学生の時に見たジャポニカの百科事典です。「未来の家」というタイトルのカラーのページで、当時、畳と縁側のある、いわゆる日本家屋に住んでた私にとっては、きわめてインパクトのあるイラストでした。宇宙の家とかではなく近未来の家とでもいいましょうかね。
その時からこのような家を作りたいと思うようになり、当初は建築家にあこがれました。その後、絵を描くことが好きだったため中学、高校と美術部に席を置き、高校卒業後は、当然のように絵を描く道を選びました。
どちらかというと公務員のご家系だったそうですが、ご家族の反対はありませんでしたか?
それが、不思議と反対されませんでした。サラリーマンになるのはいやでしたから、迷うことなくデザインの道を選びました。
進学した美術の専門学校(名古屋)のクラスには40人ほどの同級生がいましたが、いまではデザインで飯喰っているのは、私一人になりましたね。
それは、デザインでは喰っていけないということですか?
名古屋という土地柄のためか、近くの瀬戸多治見から、陶芸の絵付けや釉薬の勉強に来ている人もいましたが、そういう人以外はやめましたね。私の場合、運がよかったんでしょうね。専門学校卒業後の若いときに徹底的に鍛えられたのがよかったんでしょう。
21歳のときに熊本市内のデザイン事務所に入ったのですが、そこで徹底的に“基礎”というか“基本”をたたき込まれました。ほとんど“軍隊的”ともいえるような事務所でした。まず最初に身についたことは、決して音を立てずにドアを開け閉めすることです。鉛筆の転がる音ですら立ててはいけないようなデザイン事務所でした。“デザイン事務所”と聞くと、一見華やかで自由な職場のイメージを持たれるかも知れません。確かに華やかな事務所もありますが、私のいた事務所はそれとは正反対で、礼儀とか上下関係を重視し、かなり緊張感のある事務所でした。
デザインの“基礎”とは?
一言でいえば“平面構成”です。たとえば、地ビールのラベルのデザインを依頼されたとします。まずはビールから連想する言葉を挙げていきます。“枝豆”、“夏”、“ジョッキ”・・・などなんでも挙げていきます。この言葉数は、多ければ多いほどよいわけです。次に消去法で絞り込みながらよりシンプルにしていきます。そうして最後は、○と△と□でいかにシンプルに表現できるかです。
もともと私は、作業をする人間としてデザイン事務所に入りました。ロットリングというペンと、三角定規と、カッターナイフを手にひたすら作業をしていました。デザイン事務所にはデザイン部門と作業部門とがあり、版下を作ることが作業部門の主な仕事です。当時はまだコンピューターは導入されておらず、0.1mm太の線を0.5mm間隔で引くような仕事を延々やっていましたよ。
 |
←第1回スウィッチ・グラフィック展に出品したポスター |
|
大田黒さんが手がけた仕事例→
|
 |
嫌になりませんでしたか?
はっきり言って、単純作業です。しかしそのとき思ったんです。この仕事をきわめてみよう、そうして将来は、版下作成のためのスクールをもとうと。
デザインのためのスクールは数多くありましたけど、作業のためのスクールはありませんでした。その後コンピューターが導入されましたが、当初はラフすぎて使えませんでした、Power
Macになって、やっとデザインにも使えるようになりましたね。いまではロットリング、三角定規、カッターナイフを使っての作業はほとんどコンピューターにとって替わられました。
しかし、この作業を徹底してやっていましたからわかるのですが、コンピューターでは表現できない、人の手でないと表現できない技・味というものが、確かにあるんです。
“デザイナー”というと、「パッとひらめいてお金になる」ようなイメージがあるのですが?
そのような人はまれでしょう(笑)。
あるレストランからマークのデザインを依頼されたとします。まずリサーチしてそのお店の資料の収集です。もちろんオーナーの話も充分に聞きます。周囲からの評判も聞きます。単なるマークとお考えかも知れませんが、中身があってのマーク、中身あっての商品のラベルなどのデザインです。中身とマークのイメージがイコールでないとよくないんですね。ですから資料の収集は十分に行います。
次に、資料をもとにマークのデザインを考えますが、やはりクライアント(依頼人)には好みがありますので、候補のデザインは、必ず3つ、4つ以上は作ります。私の考えに「99%の誠意と1%の知恵」というのがあって、どれに決まっても私自身が納得がいくように、3つ作る場合、どれひとつとして手を抜くことはありません。自分に恥ずかしくないように、お客様に恥ずかしくないように、そしてどれだけ付加価値をつけられるかですね。
1つのマークのために、3倍の仕事をなさるのですか?
仕事の性質上、最初から1つしか作らないということはありませんので、「3倍の仕事をした」という感覚はあまりありませんが・・・。
デザインが決定してマークやパッケージが完成した後は、アフターリサーチです。アフターケアみたいなものでしょうか。作品を使ってもらってから、どれだけ売り上げが伸びたかとか、お客さんの評判はどうかなど、実際に聞いてまわります。そして依頼された人から「このマークにして売り上げが伸びた。よかった」との声を聞いて、やっとその仕事が終わったと思いますね。
うちの事務所は、料金が高いと言われることがしばしばありますが、一度依頼された人はリピーターになってくださいますし、たとえ見積もりをとって、ほかの事務所に仕事を出されても、また帰ってこられますね。そんなときは99%の誠意が伝わったのでしょう。
1%の知恵とは?
“知恵”とはいろいろな意味を含んでいます。もちろんひらめきもありますが、デザイナーとしての悪知恵のこともあります(笑)。候補作のプレゼンテーション(提示)のとき、クライアントからマークに対する注文、ときにははっきりと文句をつけられることもあります。そのような場合にクライアントに対して説明する知恵、反論する知恵です。もちろんデザインのプロとしての知恵ですけど。
若手の育成についてはどのように?
ただひたすら、よいものを見せることです。よいものをどれだけ見せるかです。デザインは、よいものを真似ることから始まります。しかしどんなに真似ても、最後のひとひねりがないと、単なる盗作です。
数多くよいものを見るということは、自分の頭のなかに、多くの引き出しをもつということです。引き出しが多ければ多いほどひねりもシャープになってきます。よいものを見せて実際の仕事をまかせる。たまにまかせた後のフォローが大変なこともありますが、実際にやらせないと、ひとひねりも生まれてきませんし、育ちませんね。
これからの高齢化社会や情報化社会については?
日本は単一民族単一言語の国ですので、ピクトグラム(絵文字・マーク)よりは、まだまだ日本語のほうが解りやすいようですね。今後どのくらいピクトグラムが生活の中に溶け込んでくるかは未知数です。ただし情報化社会のなかでのニーズは高まるでしょう。もしくは高まってほしいですね。
たとえば最近いろいろな企業がISOを取得し始めましたが、まだ一般の人にはピンときてないみたいです。多くの情報を一目瞭然に知らせるのがピクトグラムでありマークなんです。情報が溢れすぎている現代社会においては、ピクトグラムがよい道しるべとなり、だれもがより速くより的確に、必要な情報にたどり着けるようになってほしいですね。
日本語をアシストするサブ言語というよりも、英語と同じように1つの言語としてピクトグラムが日本社会に定着して欲しいし、定着するような良質のピクトグラムを我々が作っていかなければいけないと思っています。
 桜歯科のマークや患者さん・業者さんたちへの諸案内状(ハガキ)、筆者の名刺などのデザインも、大田黒さんにお願いしました。ハガキが送られてくるのを心待ちにしていてくれる人もたくさんいます。よいデザインは一人歩きするものだとつくづく感じます。素晴らしい補綴物が一人歩きするのと同じことなのでしょう。
桜歯科のマークや患者さん・業者さんたちへの諸案内状(ハガキ)、筆者の名刺などのデザインも、大田黒さんにお願いしました。ハガキが送られてくるのを心待ちにしていてくれる人もたくさんいます。よいデザインは一人歩きするものだとつくづく感じます。素晴らしい補綴物が一人歩きするのと同じことなのでしょう。
大田黒さんのお話の中の“マーク”を“補綴物”に置き換えると、そのままわれわれの仕事に通じるお話だと思いながら、インタビューを終えました。
|
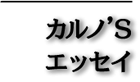






 桜歯科のマークや患者さん・業者さんたちへの諸案内状(ハガキ)、筆者の名刺などのデザインも、大田黒さんにお願いしました。ハガキが送られてくるのを心待ちにしていてくれる人もたくさんいます。よいデザインは一人歩きするものだとつくづく感じます。素晴らしい補綴物が一人歩きするのと同じことなのでしょう。
桜歯科のマークや患者さん・業者さんたちへの諸案内状(ハガキ)、筆者の名刺などのデザインも、大田黒さんにお願いしました。ハガキが送られてくるのを心待ちにしていてくれる人もたくさんいます。よいデザインは一人歩きするものだとつくづく感じます。素晴らしい補綴物が一人歩きするのと同じことなのでしょう。